

kickoff ブログリレー 学年リーダー 八代亜慧
平素より南山大学男子ラクロス部を応援していただきありがとうございます。 3年学年リーダーの八代亜慧です。 ブログを書くのは初めてで拙い文章ですが最後まで読んでいただけると嬉しいです 僕は昨年の1年の夏に怪我をして1年間ラクロスをしておらず実際学年リーダーを担う上で実力も大き...
2020年12月8日


kickoffブログリレー 学年リーダー 伊藤翼
平素より多大なるご支援、ご声援ありがとうございます。 初めまして、1年生学年リーダーを務めさせていただく伊藤 翼と申します。 ここではチームとして掲げている『学生日本一』のために何をするべきか 僕なりに考えたことを書いてみたいと思います。...
2020年12月7日


Kickoffブログリレー 学年リーダー 三浦敬至
平素よりお世話になっております。21南山で学年リーダーを務めます。三浦敬至です。コロナによっていろんなものが隔てられ、当たり前にあったものが目に見えて機能しなくなっていく様を見て、改めて毎日ラクロスができていることに幸せを感じています。...
2020年12月6日


kick offブログリレー DFリーダー 佐波竜太郎
OB、OGの方々、先輩、保護者の皆様、 その他多くのラクロス部に関係する方々の支援により活動できていることに感謝すると共にお礼を申し上げます。ありがとうございます。 21南山DFリーダーを務めさせていただくことになりました、佐波竜太郎です。...
2020年12月5日
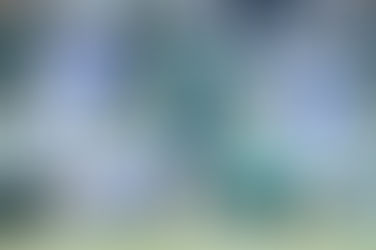

kickoffブログリレー FOリーダー 家木笙太
平素より多大なるご支援、ご声援、ありがとうございます。今シーズンのFOリーダーを務めさせて頂く家木笙太です。 僕は自分の意見をあまりチームの皆に言ったことはないですが、キックオフブログという良い機会を頂いたので、僕が「学生日本一」という目標について考えている事を書いてみたい...
2020年12月4日


kickoffブログリレー MFリーダー末廣太一
平素より多大なるご支援、ご声援ありがとうございます。 今年度MFリーダーを務めさせていただく末廣太一です。 とは言いましても、現在僕は絶賛入院中でありまして、 MFリーダーらしいことはまだなに一つできていないのが現状です。 (僕もこの写真好きよ、リクトくん)...
2020年12月3日


kickoffブログリレー ATリーダー 野々部颯
平素より南山大学男子ラクロス部の活動への 理解、ご支援・ご声援をありがとうございます。 21南山でATリーダーを務めます野々部颯です。 ブログを書くことは 引退するまではないと思っていましたが、 せっかくの機会を頂いたので 僕の今思うことを伝えれたらいいなと思います。...
2020年12月2日


kickoffブログリレー TRリーダー 尾関由真
南山大学男子ラクロス部に関わってくださる皆様、日頃より多大なるご声援・ご支援を頂き本当にありがとうございます。この場を借りて御礼を申し上げます。 今年度、TRリーダーを務めることになりました尾関由真です。 怪我で悔しい思いをして欲しくない。...
2020年12月1日